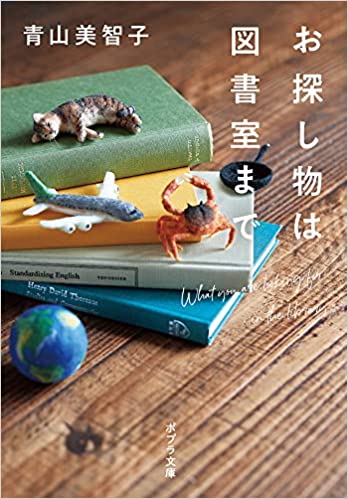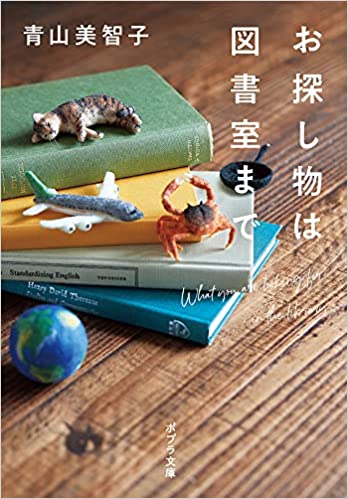
お探し物は図書室まで 青山美智子 ポプラ文庫
最近、「本の処方」みたいなことをできないかと考えております。そういえば、『文学効能事典』という本があり、「○○のときにはこの本」といった感じに世界の文学作品が並べられています。
そんな感じで、まずは相手と対話して、「こんな悩みの人にはこの本」「こう考えている人にはこの本」と、自分の知っている本の範囲で薦めてみたいですね。
実用書や自己啓発書は即効性のある(実践すれば)薬だと思います。それに対して、古典や小説の場合には即効性はないかもしれませんが、体質改善というか何というか、頭を根底からちょっと変えてくれるものと感じます。たとえてみれば、栄養療法や運動療法のような。
栄養療法、運動療法にしても、継続が大切です。習慣ですね。つまり、読書の習慣です。
本を処方するにしても、患者さん(?、“クライアント”でしょうか)の訴えや困っていることに対して、もちろん即効性のある実用書や自己啓発書を処方することもあり、または長期的な効果を期待して古典や小説を処方することもあり。そんな感じで本を紹介することができればと思っていました。
*
そんなことを考えているときに読んだのがこの本です。この物語を読んで、また違ったカタチの紹介のしかたがあることに気づきました。
実用書や自己啓発書のように実用性、即効性を与えるわけでもなく、それでいて古典や小説のように、読み続けることによって徐々に心と体が変わってくるのを期待するのでもない。
いってみれば、“オフセット紹介”といいますか。・・・うーん、自分でも上手く表現できない。相手の悩みにズバリと立ち当たるわけでもなく、なんとなくでもなく。
相手が、紹介された本の内容と自分の問題点との関連つまり“紐づけ”に気付く、自分の問題点の見かた、捉え方に新たな一手を与えてくれるような。そんな感じの本の紹介があるのだなあ、と感じました。
*
この物語では図書室の司書さんが、問題をかかえて訪れた人間に対して、その問題に直接かかわるような本数冊とともに、「え?」と思うような本を1冊紹介しています。
そして、その1冊がやがて問題を解決してくれるというか、その人間の内面を掘り起こし、勇気づけ、問題と対峙していく力を与えてくれています。
ただ、その意外な1冊から自分が何を感じられるか、自分の陥っている局面においてどのような意味があるのかを知るセンスは、もともとそれぞれの人間に備わっていたもの、あるいはそういう局面だからこそ受容できるものではないでしょうか。
探しているものは、自分の中にあった。それを気付かせてくれるきっかけとしての本。もちろんきっかけとなるのは本だけではなく、人との出会いや異なる環境などもあるでしょう。
そう言えば、出口治明氏のおっしゃる「本、人、旅」というのは、自分の中に眠っている自分を発掘するための“きっかけ”のことなのかもしれません。
そう、そんな感じで本の紹介ができればいいな。私はこの本を読んでそう思いました。
「どんな本もそうだけど、書物そのものに力があるというよりは、あなたがそういう読み方をしたっていう、そこに価値があるんだよ」(P175)
本には「読み方」としての方法論、つまり速読や遅読、熟読、積読などがまずあります。一方で自分がその本に対してどのように読めるかという「読め方」もあると思います。
読み方については、自分なりに編み出したり、それこそ読書術の本を読んで勉強したり他人に聞いたりすることで身につけることができるでしょう。いわば、読書における外発的要素と言えるでしょう。
一方で、読め方というのは、聞き慣れない言葉かもしれませんが、ある本に対して個人個人がどのようにそこから読み取ることができるかということです。
これは往々にしてその読者の力量によります。力量といっても読解力や集中力というわけではなく、知識や経験、あるいは思考パターンや感情などによるものです。いわば、読書における内発的要素と言えるでしょう。
同じ小説でも、たんにサラッと面白い話だったね、と読む人もいますし、一方で自分の過去の経験や境遇と内容が酷似していて、自分のことのように読めてしまう人もいるでしょう。
あるいは、これから仕事をどうしようかなどと悩んでいる人とそうでない人にとって、同様の悩みの中にある主人公に対する思い入れは、まったく異なるものでしょう。
自分は他人と違って、この出会った本をどのように“読めた”か、それが本の価値であり、それを個々の読者が感じて活かすことが、読書の意義の一つだと思います。
「私はね、権野さん。人と人とが関わるのならそれはすべて社会だと思うんです。接点を持つことによって起こる何かが、過去でも未来でも」(P302)
前に述べた、「本といかに付き合い、自分がどのようにその本を読むことができたか」は本に限らず、人についても同じですね。
出会った人に対してどのように付き合ったか、どのようなことを知ったか、そして自分の人生にどう影響したか、どのように活かすことができたか。
まさに、本は人であり、読書は人生であります。
また、たとえば歴史を知ることは、時間を超えたより広い人との関わりを少しなりにも持つことであり、時間を超えて自分の社会を形成することだと思います。
自分の周囲の世界が時間的にも広くなるわけです。これは史実とされる歴史だけに限らず、歴史小説のように一部フィクションを含んだものでもいいですし、小説のようにまったくのフィクションでもかまわないでしょう。
現実であれフィクションであれ、そこに登場する人とのつながりが少しでも自分にできれば、感じられれば、自分の周囲の社会は広がり、つまり世界が広がる。これは自分の思考の幅が広がることと同義だと思います。
そう考えると、歴史を知るにしても、物語を知るにしても、あるいは人を知るにしても、やはり読書は最強であり、自分の社会を広げてくれる人生の大切なツールですね。
「でもね、私が何かわかっているわけでも、与えているわけでもない。皆さん、私が差し上げた付録の意味をご自身で探し当てるんです。本も、そうなの。作り手の狙いとは関係のないところで、そこに書かれた幾ばくかの言葉を、読んだ人が自分自身に紐づけてその人だけの何かを得るんです」(P313)
ほとんどの場合、文字だけの文章からなる本。文字から頭の中に起こされる映像は、往々にして読者の知識や経験、想像力に任されます。表紙に絵があると、それによる影響も大きいでしょう。
そんなとき、この物語のように本の付録としてこういったオブジェクトがありますと、それもまた読者の頭を耕してくれるものと思います。
それを的確にセレクトする司書さんにも脱帽ですが。
*
そうですね。こんな感じで、紹介した本からも自分なりに紐づいた読め方をしてもらい、その時の心境、境遇に合ったメッセージを得てもらえるような本の紹介をしたいです。
我々は小学校あたりからテストや試験や入試など、なにごとも「問い」が与えられたら「答え」があるもので、それを答えなければならない思考に陥っています。
そんなパターンは全てに当てはまるわけではありませんし、第一、その「問い」を作るのが大変なんですよ。
そういったパターン思考に陥ったままで本なんか読み出しますと、「この本からはこういう考え方を学びとらなければならない本だ」とか、「この小説はベストセラーだから面白いんだ(面白く感じないと自分がおかしいんだ)」などとヘンチクリンなことを考えてしまうのです。
得体のしれないものから、いかに引き出すか。いかに「問い」を自分なりにこしらえ、自分なりに本から切り取るか。これは人を相手にするときも同様、世界を相手にするときも同様です。
そのようにして、本なり人なり世界なりに対して自分なりの切り口で当っていくと、おのずと「自分はこういう感じで本や人や世界に当たっているんだ」という、自分の立ち位置、軸みたいなものも感じることができてきます。
これがまさに、「ご自身を探し当てる」「自分自身に紐づける」ということではないでしょうか。