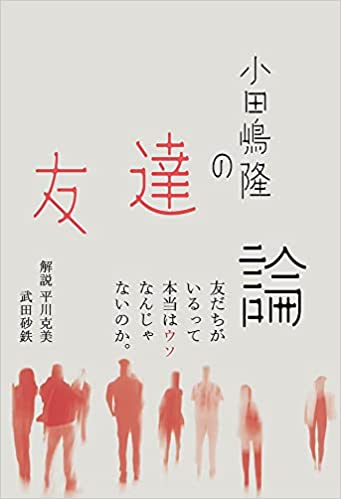
小田嶋隆の友達論 小田嶋隆 解説 平川克美 武田砂鉄 イースト・プレス
さて、いま現在、自分には「友だち」と呼べる人間はいるだろうかと考えました。
もちろん職場には日々顔を向き合わせる人々がいるわけですが「友だち」というわけでもなく、そもそも仕事の人間関係は「友だち」ではないでしょう。
家族も「友だち」ではないし。やはり仕事や家庭とはまた違った関係で繋がっている人を、「友だち」と呼ぶのでしょうね。
かといって私の趣味は自慢できるほど個人競技が多く(読書、自転車、筋トレ、弓道、フルートなどなど)、一人でノホホンと楽しめるものばかりです。これが読書会やツーリングやジム、合奏団などに参加すれば、それなりに人づきあいは発生するのかもしれませんが、あまり乗り気ではありません。
と、なると、やはり旧友といいますか、昔から付き合いのある人や、昔付き合った人の中に「友だち」を見出そうとします。幼少時、小中高校のときのクラスメート。もちろん大学でも友だちと呼べる人間はできるでしょうが、年齢が上がるにつれて勉強や部活の人間関係のうえでという感じがします。
うーん、いるかなー、いないなー・・・。あっ、このブログを読んで見てくださっている皆さんも、ある意味「友だち」と思ってます!
(『友だち幻想』の紹介記事もご参照ください)
*
さて、今回ご紹介するこの本は、そんな「友だち」について再考させてくれます。本当に「友だち」と感じられる人物とはどのようなものなのか。「友だち」はあった方が良いのか、そうでもないのか、など。
著者の小田嶋隆氏はコラムニストとして、多くの文章や著書で「世の中本当にそうなの? それでいいの?」と問うてくれた方だと思います。残念ながら2022年に逝去されております。
この本を読んで良かったことは、「本当の友だち」とはどういうものか、よく考えることができたこと、そして私のようないわゆる「友だち」が少ない人間も、安心して余生を生きることができ、半生を振り返ることができるようになることです。
大切なのは、それぞれの「友だち」の名前や個性ではない。知り合った時期と、過ごした時間が代替不能だということだ。相手は、むしろ、誰であってもかまわない。あくまでも重要なのは、10歳の時に知り合って、そのかけがえのない時期を共に過ごしたという事実だ。(P21)
「友だち」とは付き合った当時のかけがえのない時間を一緒に過ごした事実があり、同時にそのことを思い起こさせてくれるものなのですね。ひいては自分の記憶やアイデンティティ、つまり自分とはこういう人間でこのように生きてきた、を呼び起こしてくれる存在です。
人生の一時期を思い起こさせてくれるという意味では、「友だち」は人生の「栞」と言ってもいいのではないでしょうか。
もちろん、ある時期に聞いた音楽あるいは写真なども、ふと聞き返し見返すと往時の記憶がよみがえることがあり、音楽や写真も人生の栞と言えるでしょう。
でも「友だち」は音楽や写真よりもおそらく長く時間を過ごしたでしょうし、音楽や写真よりも一時の感情だけではなく起伏に富んだ感情の変化や時間を過ごしたのではないでしょうか。
栞は、本に挟むことでどこまで読んだかを記録しておくことができます。その栞を見返すことで、物語が再開されます。同様に「友だち」も、その人のことを考えることにより人生の一時期が想起されます。
それが、「友だち」と呼べる人間の一要素なのですね。
すなわち、人と人とが親しく語り合うためには、高度なボキャブラリーは不要だということだ。抽象的な単語や、知的なボキャブラリーは、初対面の人間同士が打ち解けるためには、むしろ障害となる。(P93)
例えば言葉の通じない外国の人とコミュニケーションするとき、高度なボキャブラリーで言語的な対応をするよりも、表情やジェスチャーなどを駆使したほうが打ち解けるとのことです。
人と人とのコミュニケーションには、基本的に言葉が用いられます。さらに言葉によって上手に(?)コミュニケーションができないことをコミュニケーション障害(コミュ障)などと呼んだりします。
でも、非言語的コミュニケーションというのもあるのです。笑顔などの表情や身振り手振りといったジェスチャーといったものが含まれます。
言葉には限界があります。言葉は単に発した人の頭の中の一部を表現しているに過ぎません。また、受け取る人もその言葉の持つ意味をすべて受け取り、理解できるわけではありません。
そういった問題は抽象的な単語や知的なボキャブラリーとなると、程度を増すでしょう。相手に理解しにくくなったり、間違った解釈をされたりします。
かといって言葉は有力なツールですから、とりあえず言葉も使いますが、同時に非言語的なツールを使うことで、言葉が乏しくても打ち解けることができるのです。
歌や音楽も、世界共通のコミュニケーションツールと言ってもいいかもしれません。たとえ相手に歌詞は分からなくても歌を歌ったり、楽器を奏でたりすることは、相手の心に思いや感情を届けます。
そして、そういった非言語的コミュニケーションの効果が、最大限に発揮される関係が「友だち」なのだと思います。もちろん、場合によっては恋人や配偶者もそうかもしれません。
*
そう考えてみますと、一般的な初対面でも言語的なコミュニケーションにだけに頼らずに非言語的ツールを加えるほうが、なんとなく上手くいくのかもしれませんね。
どうしても我々は、初対面時は名刺を渡し、そこに書いてある言葉を読みとります。また、会う前も事前にネットなどで調べて、そこにある画像や言葉から相手のことを知ろうとします。
そういった情報もある程度役立ちますが、やはりそこは言葉あるいはせいぜい写真や動画からの一方的な情報になります。
名詞にもちょっと好きな歌や映画、趣味を書いておくことや、どんなことに感動したかなどの話題を出してみるのも、早く打ち解けるために良いのではないでしょうか。
「天気の話」が人と会ったときの話題として優れているのは、晴れなら良い気分、雨なら嫌だなーという気分、あるいは暑い寒いといった感情や感覚が共有しやすいというのもあるかもしれません。
京都が特別な土地だという話をしているのではない。私は、30年ぶりに訪れる土地には、30年分の記憶が冷凍保存されているということを言おうとしている。(P226)
記憶は記銘、保持、想起からなります。見たことや聞いたこと、読んだことなどを頭の中に入れることが記銘。その内容を時間がたっても保っておくのが保持。そして頭の中に無意識に記憶、保持された内容を意識に上らせる、あるいは言葉にしたり文字にしたりと表現することに関わるのは想起です。
よく「忘れた」と言います。これは記銘できていなかったり、保持できていなかったりもありますが、頭の中に入ってはいても出てこない、想起できないだけだったりすることもあります。
一方で、想起できなくて意識に上らない記憶でも、無意識の世界には存在し、その人の思考や行動に影響を与え続けていることもあるでしょう。
*
記憶の想起にはカギが必要です。記憶を呼び出すキッカケですね。
そういった外部にある想起のキッカケとなるものも、記憶の一部といってもいいかもしれません。そういった意味では、言葉や音楽、写真などのモノもまた記憶を宿すと言えるでしょう。記憶は自分の頭の中の話だけではないのです。
「友だち」の記憶も、その人物としての記憶だけでなく、たとえば一緒に遊んだ街並み、学校、公園、河原、あるいは一緒に遊んだゲーム、読んだ本など、様々な場所や光景、モノやイベントが「友だち」と結びついて記憶されていると思います。
*
さらに、そういった場所や光景、モノが、往時と変わらず存在するのを見るとき、往時の「友だち」もまた記憶から想起され思い出されます。まさに、記憶が場所やモノに冷凍保存されていると言えるでしょう。
そして匂い、光りの加減、周囲や床のきしむ音、戸の建付けなど、身体感覚も記憶を蘇らせます。
東野圭吾さんの小説『変身』でも、頭の中は変わっても、身体感覚として自分の家が分かる、という話があったと思います。
(『変身』の紹介記事もご参照ください)
その環境に身を置くことによって、頭の記憶のみならず、身体感覚の記憶、いわば「身体の記憶」が蘇るのですね。
身体の記憶というと高度な技術の習得や“慣れ”を連想しますが、こういった記憶の糸という役割もあるのです。
*****
話は変わりますが、この本の個人的な最大の謎は、タイトルでは「友達」を使用しているのに、本文では「友だち」を使用しているところです。まあ、「論」につなげて熟語にするには「友達」が良いのかもしれませんし、とくに大きな意味はないのかもしれません。
私としては「友だち」は、いま流行りの「ひらがな」による“やわらかさ”、“あいまいさ”も付加され、広い意味に捉えることができる感じがします。
「友達」というと、しっかりした交流があり、わりと長い期間で続いているような関係。「友だち」というと、そういった関係も含めて、片思い的にこちらがそう思っているだけでも含める、あるいは今は付き合いが無いけれど昔付き合ったことがあって、ときどき思い出されるような関係でも大丈夫、そんな感じがします。
アドラーのいう人生の3つタスクは仕事、愛、交友でありました。仕事、愛はなんとか務めて得られるものかもしれませんが、交友とくに「友だち」というと、ある程度は自分の記憶の強さや“思い込み”も必要なのかもしれませんね。(「愛」もけっこう“思い込み”が必要ですが)