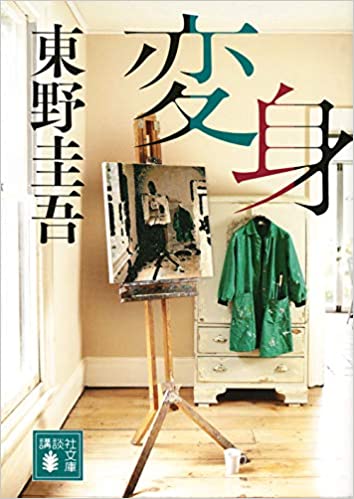
変身 東野圭吾 講談社文庫
脳の移植はできないと思う。技術的にはできるのかもしれない。神経やら血管やらをうまくつなげれば、他人の脳でも使えるのかもしれない。
でも、それでは自分ではなくなってしまう。脳をくれた他人になってしまう。みんなそう考えるだろう。
脳を移植してしまうと、どうなるか。どういうことが起きる可能性があるか。空想上ではいろいろ考えてみていたけれど、空想の域を超えない。
それを検証するのに、小説やドラマ、映画などはもってこいである。ただ、そこには作者の知識程度の問題、解釈が入ることには注意が必要だ。
それでも、こういったことをテーマにした話が、どのような話になるのか。ただその興味もあって読ませていただいた。
最近読んだカフカの『変身』と同タイトルであったことにも惹かれた。二作品の比較については、当記事の最後にも少し書いておく。
「それはやめた方がいい。脳移植には、氷山のように大きな問題が潜んでいる。その一つに個人とは何かということがある。それが解決するまでは、おそらく今世紀中は解決しないと思うがそれまでは、脳の元の持ち主について詮索すべきではない」(P59)
個人とはなにか、いかに自分が他人とは違うかというところを、どうやって決めているか。意識としての個人を規定しているのは、脳だろう
しかし、身体としての自己と他者を規定しているのは、免疫系である。この辺は、『免疫の意味論』を参照されたい。
個人個人の違いはなにか。各人の脳の機能が違っているというだけではないと思う。つまり、他人がその人をどう捉えているか、ということも考える必要があるだろう。
*
人は、周囲の他者一人一人に対して“分人”を備えている。上司に対する分人、部下に対する分人、親に対する、配偶者に対する、子供に対する分人。(『私とは何か』の紹介記事もご参照ください)
さらに、周囲の人たちも自分に対する分人を備えてくれている。
脳が変わったといって、自分だけが変わっても、周囲の人が持っていた自分に対する分人は、すぐには変わらない。あらためて新たな自分の分人まで方々の人々に創ってもらうことができるか。
パッと脳を変えれば、その個人になれるわけではない。周囲の人に、その個人に対する分人も創らせて、やっとその個人が人間としてやっていけている。
人間は、自分だけで生きているのではない。
「ジュンの頭には、誰かほかの人の脳が少し入っているのよね」
「そうだよ」
「でもジュンはジュン……よね」
「何をいっているんだ。僕は僕さ。ほかの誰でもない」
「だけどもし、脳を全部取り換えたらどうなるの? それでもやっぱりジュンなの?
「それは……」僕は少し考えてから、「僕ではないだろうな」と答えた。「それは当然、元の脳の持ち主なんだろうね」(P95)
ジュンが、他人の脳を移植された主人公である。こういった描写は、本当にそう思うのか、感じるのかは分からないが、そうかもしれないなと、可能性として楽しむことができる。
でも、実際にこんなふうに思うのではないだろうか。自分の中に他の人間が一部存在するような感じ。
この主人公の場合は脳の一部に他人の脳の一部を移植しただけであるから、基本的には主人公の意識になっているが、そこに他人の意識というか思考が、時々入るらしい。
*
でも、普通?の我々もこういうことは時々あるのではないか。よく“頭の中で天使と悪魔が戦っている”とか、“もう一人の自分が空から眺めている感じで大局的にみる”とかいうやつ。
主人公のように、違和感を覚えるほどではないだろうが。
考えてみると、自分でも自分の脳みそのことを隅から隅まで把握しているわけではない。どこぞやに潜在意識とか集合的無意識というのもあるらしい。忘れている記憶もあるだろう。
スーパーコンピュータMAGIだったか、三種の“性格”を備えるコンピュータ3基が葛藤のもとで決議を行うシステムがあったと思う。
世の中、なにごともすんなり決まるものだけではない。答えの無い問いに対して、分からないけどこれが最適解ではないか、という解を提案する場合も多い。
自分が意識的に決意的に決めるだけではなく、こういった無意識や“もう一人の自分”の意見を聞いてみるのもよいだろう。
だが俺はこの家から非常に強いエネルギーが発せられていることに気づいていた。それは俺の精神に働きかけ、今まで味わったことのない心の安定を感じさせた。(P241)
「ごまかせると思ったかもしれないが、あんたたちには二つの誤算があった。ひとつは俺の人格が京極の影響を受け始めたことだ。そしてもう一つは、現在の科学で割りきれないものの存在を無視したことだ」
「科学で割りきれないもの?」
「直観さ」と俺は自分の頭を指先で叩いた。(P255)
「直感」はどこからくるのか。これも、脳だけでなすものではない気がする。身体性というか、身体の感覚も必要だろう。さらには内臓感覚のような、身体全体が感じるものではないか。
脳は脳のみで人間を生かしているのではない、様々な身体部分からのインプットを統合し、身体部分にアウトプットを送る。
脳そのものは平然と静かに過ごしている雰囲気でも、状況により心臓はドキドキし、おなかは減り、腰は痛くなる。
それと同時に、脳で意識はされなくても、身体が感じるというか反応することもあるだろう。実家に帰ったときの空気感、新しい職場への慣れ、なんとなく感じる嫌な雰囲気など。
もしかして、脳の機能の意識されていない部分、つまり潜在意識とか呼ばれるところから湧き出てくるものかもしれない。
それにしても、脳単独ではなく、胃腸や手足の感覚なども重要な役割を演じていると思う。
*
さらに、ここで言われているように“現在の科学で割りきれないもの”もあると思う。
我々は科学で割りきれるものだけを確かなものとして考えているが、けっこう我々の考え方や生き方は“確かなもの”ではない。
あやふやなところがあり、行き当たりばったりのところがあり、結果オーライ的なところもある。
半分とまではいかないかもしれないが、けっこう「直感」で決めた選択肢を、これまで選んで生きてきたきがするだろう。
この物語でも、そんな「直感」が、一部が変化してしまった脳に関係なく主人公を動かしているのかもしれない。
「そうだろうか? 私は正常な欲求だと思うがね。心臓や肝臓の移植を望むのはよくて、脳なら異常だということになるのかね」
「異常なことだということを、この俺が証明している。なるほど新しい脳を手に入れることは可能だろうが、昨日までの自分と違ってしまっては意味がない」(P260)
肝臓、腎臓、肺、心臓などの移植は行われている。それによって病状が改善したり、命を長らえたりする人がいるのも事実である。
肝臓や腎臓と脳の違いはなにか。カタチや外見において個人差は少ない。さらに、機能においても、たいてい全ての人の臓器が同じような働きをしている。
もちろん多少の大きさの違いや、酒に強かったり心臓に毛が生えていたりといった違いはあるかもしれない。
では、脳の場合はどうか。こちらもカタチや外見には大きな違いはなさそうである。アインシュタインの脳は見た感じシワが多くて少し大きいという話もあるが、そのくらいである。
しかし、機能においてはどうか。脳の機能の違いが、いわば個人の人間としての違いを表している、といってもいいのではないか。
もちろん、大きな見方で生物としての人間を考えれば、生命維持や本能、運動・感覚といった動物にも共通する機能から、情動、記憶、学習など人間で発達した機能を備えているという点では、どの人間の脳も大差はないだろう。
でも、各人の脳が各人の“個人としての人間”を表しており、各人の生き方、考え方、人生を形作っているとも言えるのではないか。そんなフシギな臓器なのである。脳というのは。
生きているというのは、単に呼吸をしているとか、心臓が動いているとかってことじゃない。脳波が出ているってことでもない。それは足跡を残すってことなんだ。後ろにある足跡を見て、たしかに自分がつけたものだとわかるのが、生きているということなんだ。(P257)
「廃人といっても、それはこの世界でのことにすぎない。この世界で生きることはできなくなっても、無意識の世界で成瀬純一は生きられるのです。その証拠に彼は消えずに、こうして俺を呼びに来てくれました」(P379)
周囲への影響を残してきたこと、周囲の人に影響を与え、変えてきたこと、それが生きているということだ。
先ほど、分人の話を出したが、自分が周囲の人に対して分人を備えるように、周囲の人も自分に対して分人を用意してくれる。
生きているということは、何らかの相互作用を周囲に及ぼし、自分も変わるが相手も変わる。そうやってお互いに影響し合って、変え合っているのが人間をはじめとする生物だろう。
*
たとえば自分の死の間際、あわよくば近しい人が周囲に集まってくれているとうれしいが、そこで思うことは、こういった人たちに、自分は影響されてきて、そして自分も影響を与えてきたのだ、といった感じかもしれない。
もしかして“走馬燈”とは、その映像化なのかもしれない。
たとえ寝たきり、はたまた意識の無い状態になっても、存在しているだけで、周囲の人は、自分がその人に影響されてきたこと、自分も影響を与えてきたことが、“生きた実感”として思い出以上に考えられるだろう。
アドラーのいう、「存在するだけで意義がある」にも繋がる考え方である。なにも華々しい功績を上げて周囲の人を幸せにしてあげるだけが生き方ではない。
存在しているだけで、生きているだけで、親は子をみて自分の生きた道を確信し、子は親を見て自分の進む道を安心できるのである。
*****
私はこの小説を、カフカの『変身』との比較で考えてみたことがある。
カフカの『変身』は、意識というか脳は変わらず、身体が変わっている。それに伴い、変身したザムザの行動も身体に引きずられて次第に変わっていく。
おそらく、変化した身体行動様式は次第に考え方、生き方も変えていくだろう。
一方でこちらの『変身』は、身体はかわらず意識というか脳が、完全にではないが変わっている。
しかし、変わった脳が意識や行動を次第に変えていくのではなく、それに抗って身体性や身体感覚、「直感」が主人公をもとの人間に保とうとしているように思える。
“中枢は末梢の奴隷である”という言葉もある。脳というのは身体を統治しているように見えて、実は身体の各部、各臓器と同等の位置、あるいはむしろ扱き使われている感じなのかもしれない。
*
世の中は脳の代替のようにAIを拵えようとしているが、脳の計算機能の拡張としてAIに期待するだけであれば問題ないだろう。
しかし、人間の脳の素晴らしげに見える機能は、脳だけで執り行っているのではない。脳が思うようにはいかない、ドキドキしハラ減りしくしく痛む、”ままならない”身体が、その時その時に応じて反応し、脳と協力して過ごしているのである。
この身体性、身体感覚、「直感」というものは、なかなかAIならびにキカイには難しい代物だと思う。
逆に、こういったところを生かすことが、今後もAIに負けずに人間が過ごしていくポイントかもしれない。