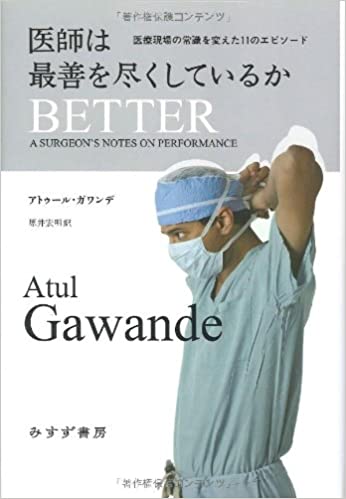
医師は最善を尽くしているか アトゥール・ガワンデ みすず書房
この本は、医師の患者に対する姿勢や考え方、著者が「パフォーマンス」と呼ぶものについて、実践例をふんだんに取り込んで書かれた本です。
医師としての根本的な姿勢や倫理観については、「ヒポクラテスの誓い」や「ヘルシンキ宣言」がよく知られています。
しかし、日々の臨床における実践的な行動、つまりパフォーマンスについては、あまり具体的に提示された本は少ないと思います。
それはどうやって勉強すればいいのか。上級医の背中を観ることも一つかもしれません。医療系ドラマや小説、あるいは医師の記述による書物を読むことも、一つかもしれません。
そういった中でこの本は、熟練の外科医である著者が自らの体験から、あるいは周到なインタビューと調査から、パフォーマンスについての「逸話」を取り揃えてくれています。
「まえがき」でも著者は以下のように述べています。
この本は医療におけるパフォーマンスについての本である。
・・・医療において、どんな職種でもそうだが、われわれはシステムや資源、状況、人々と取り組まなければならない。そして、自分自身の弱点も対象になる。
・・・われわれがどう取り組み、なにをするかが、この本で私が書こうとしたテーマである。(まえがきvii)
*
医師の仕事は、知識と技術を駆使するという面もありますが、それだけではありません。まあ、どんな仕事でも同様でしょう。
いくら良い包丁や調理技術を持っていても、それを工夫したり場面を考慮したりしないと、食べる人の満足する料理はできません。
この本は、知識や技術を駆使するための医師の姿勢、考え方、行動といった違った面から、医師の仕事を観ることができる良書だと思います。
持っている知識や技術をどう使うか。職場環境の違い、設備の違い、同僚や上司・部下、コメディカルの違い、あるいは日々場面ごとに生まれてくる自分の気持ち、感情、考えとどううまく付き合っていくか。
「訳者あとがき」にもありますが、この本は医学生や研修医にぜひ読んでほしいと思います。
作中の医師にあこがれを感じるのもいいでしょうし、なにより、医師という職業のあまり意識されていない、かつ重要な側面が、感じられると思います。
もちろん、一般の方にとっても、医師の仕事を通して医療を取り巻く社会や病気とのつきあい方などを知ることができる本と言えるでしょう。
医療におけるパラドックスの中心は、たとえどれだけうまくいっても決して十分だとだれも言わないことである。(P92)
医師にとっての、簡単で意義深い原則は「常に戦え」ということになるだろう。何かもっとうまくやれるのではないかと探しつづけることである。(P145)
「よい医師とは、一つ大事なことを理解している人で、それは治療は医師のためではなく、患者のためだということ」(P148)
標準的な診療を行うことだけが、我々医療関係者にできることではありません。それ以上のことも、患者さんや家族に対して行うことができます。
「こうすればどうだろう」と工夫を重ねることもできます。日々の仕事から何か特徴や経過を見出し、考察することもできます。
診断に対して標準的な治療を行ったから、それでよしと満足するのではなく、「もっとできることはないか」、「調べれば何か分からないか」と探求することが大事だと思います。
患者さんや、家族も、病気のことについて今の時代すごく調べていらっしゃいます。負けずにこちらも調べて対応します。
さらに、「こうしたらいいのでは」と思うことは、明らかな害のない範囲でトライすることも、ときには考えるべきです。医療においては、ときどき“先手を打つ”ことも重要です。
そのためには、日々患者さんを観ることが一つだと思います。外来診察時との違い、入院時との違い、昨日との違い、あるいは手術や治療の前との違いに気づくこと。
こういった観察が、予定通りの診療以上のことを患者さんにしてあげれられるかどうかに関わってくると思います。
ここにパラドックスがある。医学研究に携わる医師に、現代医学の進歩はどうやって実現したのかを尋ねてほしい。エビデンスに基づく医療(EBM)のモデルについて語るだろう。
・・・一方、産科では、新しい方法について試す価値がありそうに見えたとき、産科医が臨床試験での結果が出るのを待つことはなかった。先に進んで実際に試してみて、結果がどうなるのか経過を見るようにしていた。(P172)
産科医が直面している問題はこれである―医療は職人芸なのか、産業なのか? (P174)
医療は一種の産業として、エビデンスに基づき標準的な医療(EBM)を、次々来る患者さんに施すことも必要かと思います。治療の均てん化も進められています。
一方で、最近よく言われているテーラーメイド医療のように、個々の患者さんに対応した、ふさわしい医療を考えることも必要です。
それはけっして個人ごとの遺伝子変異に基づく治療のような、科学的なことだけではなく、患者さんの性格や好み、人生に対する考え方などを汲んだ医療もそうだと思います。
EBMを補完する立場としてのナラティブ・ベイスド・メディスン(NBM)は、そういった要素も含むのではないでしょうか。
*
手術をはじめ様々な医療手技は、それこそ「職人芸」のような要素はあると思います。実際に手術してみると、患者さんの病気の場所や血管の走行など、千差万別です。
こういった個人差に対応するには基本を踏まえたうえで“感覚”や“勘”、“経験”を活かして臨機応変に状況に応じて対応できる、「職人芸」も必要でしょう。
「産業」として、すべての患者さんにエビデンスに基づいた均一な最低限の医療を届けることも必要です。
それとともに、「ナラティブ(物語性)」と、「職人芸」とも言うべき技で個々の患者さんに対応する二つの考え方が必要と思います。
今後の10年間、パフォーマンスの科学に力を注げば、ゲノム研究や幹細胞治療やがんワクチンなどメディアがニュースに取り上げるようなすべての実験科学よりも、もっと多くの命を救えるはずである。研究費をいくらかけても高すぎることはない。(P213)
自然科学としての医療は、基礎実験や臨床試験など段階を踏んで、医療に取り入れられてきました。医療の発展はこういったものに大きく依っています。
しかし、検査・治療体制や素晴らしい医療機器を備えても、それを使用する医師の姿勢、考え方、つまりパフォーマンスがそれほどでもなければ、活かすことはできないでしょう。
そういった意味でも、新しい治療法や医療機器を開発したり導入したりすることを考えることも大切です。
その一方で医師のパフォーマンスとはどのようなものか、どうすれば向上できるか、どうすれば伝えられるのか。
確かに、パフォーマンスを科学することも、医療の向上のために極めて有用と思います。
五つの答えを思いついた―価値のある違いをどうすれば生み出せるか、言い換えれば、どうすればポジティブな逸脱をできるか、それについて五つのアドバイスを考えたのである。
「筋書きにない質問をしなさい」
「不平を漏らすな」
「何か数えろ」
「何か書け」
「変われ」
(P230~)
これらは、著者が医学生に講義するにあたって考えた、アドバイスです。
この本の内容を踏まえて、「では明日からの日常業務でどう過ごしていったらよいか」がここにまとめられていると思います。
ぜひ医学生も研修医も、はたまたある程度経験を積んだ医師も、ここを読んで診療のパフォーマンス向上に生かしましょう。
一つ目について。患者さんや家族から、とくに初診のときにじっくりと問診を行います。聴き出すことは、おおよそ決まっています。
患者さんの訴えを聴き、病歴をとることは、医学生や研修医のまず修得すべきスキルでもあります。
主訴(患者さんが一番こまっている症状)、現病歴(その症状の経過や程度の変化など)、既往歴(これまで何か病気やケガなどをしたことがないか、あるいは服薬状況)、生活歴(飲酒喫煙や、職業など)などを聴取します。
(失礼な言い方ですが)慣れてくると、効率よくこれらを聴取することができます。また、効率よく聴取することが、外来業務などを時間内にこなすポイントでもあります。
著者は、それ以外のことも聴こうといっています。私もまったく同感で、これまでも後輩などに言ってきました。
「趣味でも好みでもペットでも好物でも職場の立場でも何でもいいから、直接病歴や疾患とは関係なくても何でも聞いてみよう」と。
確かに、診療には直結しないかもしれません。しかし、そうやってちょっと普通は離さないようなことを話した患者と医者の間柄は、一層深いものになると思います。
実利的には考えたくありませんが、そういったところが患者と医師の信頼関係に、少しでもつながると思います。さらに、前述した患者さんの「ナラティブ」を理解する一助となります。
*
二つ目について、これもまったく同感であり、医者になりたてか、あるいは学生の時に上の先生に言われた覚えがあります。医師というものは、間違うこともある。それは自分も同じである。
他の医者の間違いや、気が付かない点、あるいは性格が悪いだとか、嫌いだとか、あるいは病院が悪いとか社会が悪いとかあるかもしれないが、それを不平として言ってはいけない。
もちろん、飲み会などでブーブー言い合うのは構わないかもしれません。でも、私はそういう場でもあまり不平は言わないようにしていますがね。
なぜか。自分が言われるのがイヤだからというのが一つあります。自分も言われないように、人にも言わないようにしよう、と。
もう一つは、そういった不平を言っても、状況が好転するわけでもなく、ともすれば「言葉」として発することにより自分の中にフィードバックして刻み込まれ、より不平感が募ると思うからです。身体に悪いですよ。
あと、何か良くないことが起きた時に、他人のせい、環境のせい、など責任を他に預ける。これも、実際そうだとしても、どうかと思います。
なにしろ、そうしたところで自分の足しになりません。失敗したら次善策をとりつつ、反省して少しでも自分の足しにすることを考えましょう。
自分はこの経験から、次からは、どうできるだろうか、と考えるのです。
*
三つ目について。これはルーチンで日々こなしていく診療や手術や検査を客観的にピン止めして、記憶と記録に固定する手法だと思います。
手術の件数はもちろん、ある事象が起った回数など。回診やカンファで怒られた回数なんかを記録しても、自分の状況の変化や成長(?)も見えるかもしれません。
また、本編中に紹介されたアプガーのように、スコアを付けてみるのも、物事を客観的にとらえる良い方法だと思います。
*
四つ目について、このブログなどいろんなところで私も書いているかもしれませんが、やはり「書く」ことは頭の整理になり、思考を深めることや、記憶にとどめることに繋がります。
ある手術を経験して、手術記録はもちろんですが、自分なりにその手術に対する思いや、反省点、次回はこうしてみようなどと感じた点も、とにかく「書いて」おくことが、次につながると思います。
*
五つ目は、自分では自分が「変わった」と感じることは難しいかもしれません。ただ、ひたすら日々の仕事を行い、経験と反省により吸収できることを最大限にしようとする行動が、少しずつ自分を変えてくれるのでしょう。
周りに、きっと評価してくれる人はいます。人の眼を気にすることはありませんが、見守られていることを感じながら、成長していってくれればと思います。(もちろん、自分も成長したいと思います)
*****
最近、後輩にガワンデ先生の本が面白いと紹介してもらい、この本ともう一つ『死すべき定め』を読んでみました。
みすず書房さんの本は、なかなか重そうで、どうも敷居が高く感じておりました。でも読んでみると、「まさに自分が医療に対して感じていたことが書いてあるっ!」と感激しました。
著者の、「外科医で物書き」というのも、なかなか、あこがれるところであります。
それはともかく、私も最後に引用した五つのアドバイスを活かしつつ、パフォーマンスの高い仕事をしていければと思いました。
「患者さんは自分の家族だと思って接しなさい」「患者さんのためになることはないか常に考えなさい」。古来より医師が患者さんに対する姿勢については、言われています。つまるところ「最善」を考えることでしょう。
とはいえ、こちらも働き過ぎて参ってしまっては困ります。自分の身体や心の管理、あるいは家族や交友関係も含めて「最善」を導きの星に働くことです。
そのためには、著者が記してくれた「五つのアドバイス」が役に立つでしょう。