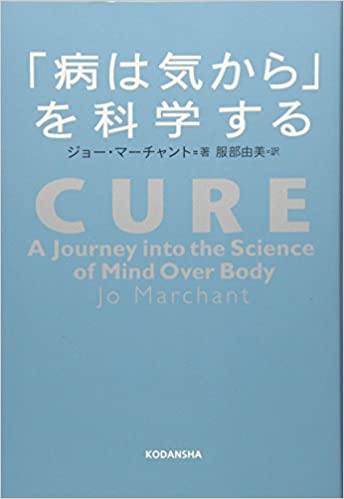
「病は気から」を科学する ジョー・マーチャント 服部由美 訳
「病は気から」という言葉がある。
一般的には病気の発症や進行は“気持ち”次第であり、気の持ちようによって良くもなれば悪くもなる、という意味だと思う。
東洋医学の観点からは、すべての現象は「気」の変化とその表れと考え、医療においても患者の「気」を整えることが大切、という意味もあるかもしれない。
精神医学的にも、「身体化」というものがあり、心の不安やストレスの影響が身体的な症状、つまり腹痛や吐き気などとして発症することがある。
*
免疫学的にみても、「気の持ちよう」は免疫系に大いに影響を与えるようである。簡単にいえば、ポジティブな気分であれば免疫も強くなるようだ。
逆に負のストレスは免疫系を弱め、他にも血圧の上昇など身体にとって様々な負の現象を引き起こす。
身体に悪い影響を与える負のストレスは“キラーストレス”などと呼ばれ、最近ではこれに対応する手段としてマインドフルネスなどにより心の持ち方を改善することも考えられている。
*
しかし、この「病は気から」にはもう一つの意味があると、私は考える。
「病になると、まず“気持ち”からやられてしまいますよ」という忠告だ。
痛みや発熱、倦怠感など身体的な症状が出現するのが最初であろうが、それにともなって「気持ち」がゲンナリしてしまう。
それが悪循環となって、「気」も乱れるだろうし、「身体化」としてさらに症状の悪化につながるのかもしれない。
もちろん、痛みなどの症状が出現した時点で、「よーし、なんとかするぞ!」などと楽観的に捉えることは難しいだろう。
*
病人は病人らしく、おとなしくしているのがいいという考えもあるかもしれない。
しかし、自然と下降気味になる病気のときの自分の“気持ち”について、「病気によって気持ちが下降するものだ」という自覚を持つ。そんなもんだ、と。
そして、少しでもそれに抗っていくことが、その後の病気の経過に良い影響を与えるかもしれない。
最近、少し体調が悪いので、そんなことを考えた。
ということで、今回ご紹介する本は、『「病は気から」を科学する』というタイトルの通り、なかば迷信の気配もただよう「病は気から」を、科学的に扱った本である。
病気とストレスなど上で述べたような気持ちと病の関係のみならず、プラセボ(偽薬)の効果、催眠術やVR(仮想現実)の応用、といった不思議な状態の科学的な検証、疲労やストレスのメカニズム、マインドフルネス瞑想法といった対応など、興味深い内容が盛り込まれている。
さらには、患者との話し方から病気治癒信仰の科学的捉え方など、だれでも経験する病気に関する様々な不思議や疑問について解説してくれる。
しかし、ここで伝えられる本当に新しい考え方は、人の心は健康について、周囲の物質界の主観的な体験よりずっと多くのことを決定しているというものだ。例を挙げれば、遺伝子発現の変化、脳の配線の仕方、世界の見方といったものも、人の体を作る働きがある。つまり、人は自分の経験だけでなく、物理的現実をも構築する役割を果たしている。すると次に、物質的な身体の健康が心の状態に影響を与える。炎症は疲労とうつ状態を起こす。低血糖値は人を短気にする。ゆっくりとした呼吸などにより、体を安定させれば、気分がよくなる。(P385)
体と心は密接に関わりあっており、心が遺伝子発現の変化や脳の配線の変化、世界のとらえ方といった物理的な変化にも影響を与えるのだ。
さらに、物理的な身体の変化が、つまり遺伝子発現が変わったり、脳の配線が変わって世界のとらえ方が変わったり、あるいは病気にかかったりすると、それらもまた心に舞い戻って心に影響を及ぼす。
様々な外的要因によって、我々の体と心はときには悪いサイクルへ傾けさせられる。疲労、突然のどしゃ降り、感染症の蔓延、あるいは仕事での失敗、不協和。
そういったサイクルに何かしら意図的に良い影響を与えるには。その両者、つまり体と心の両者に対するそれぞれのアプローチが考えられるだろう。
体に対するアプローチとしては、運動やヨガ、あるいは食生活や休息・睡眠などが考えられる。心に対するアプローチとしては、瞑想やマインドフルネス的考え方、あるいは読書があるだろう。
体と心は切り離して考えることはできないこと、切り離さずに考えるべきであることを、改めて感じる一冊であった。