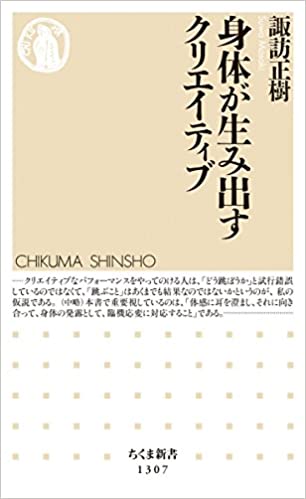
身体が生み出すクリエイティブ 諏訪正樹 ちくま新書
誰もがクリエイティブに仕事をしたい、クリエイティブに生きたい。
今まで誰も考えなかったような新たな作品、概念、考え方、物語を創出すること、クリエイティブ。そうありたいと思っても、思ってできるようなことではありません。
そう、クリエイティブは頭だけで行うものではないのです。脳だけではなく「身体」を介したプロセスなのです。
そして、クリエイティブこそが、人間とAIを分かつ特徴の一つなのです。
この本は、クリエイティブなことを生み出すうえでの「身体」の重要性に気付かせてくれる一冊です。
クリエイティブは、物理的な身体を持っているからこそ可能であり、決して、どこかで聞きかじった知識や情報を駆使するだけで(つまり概念的な操作だけで)成し遂げられることではない。クリエイティブとは身体知である。(P38)
そう、「体感」や「感情」といった、脳だけではなく身体が関係した人間の機能が、クリエイティブには大切なのです。
脳だけで机上でウンウン考えて拵えた一般的な知とは異なり、クリエイティブとは「身体知」とも言える知です。
AIは百歩譲って脳と同じ機能を持つことができるかもしれません。ところがどっこい我々の持つ脳は身体を付属しています。
そしてこの身体こそが、「体感」や「感情」と大きく関わり、クリエイティブを生み出すのです。
そして人間の思考プロセスも、「知識を適用して情報を処理する」ことだというモデル化が、現在の人工知能研究の大前提にある。しかし、羽生氏の発言やお笑い芸人たちの面白いボケやツッコミを見る限り、情報処理モデルではクリエイティブな行為を説明できないことは明らかなのだ。(P103)
この本の中には、人気テレビ番組『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』にロボットのPepperくんが出演したときの逸話が載っています。
顔認証や感情の認識、簡単な会話ができるロボットだったようですが、熟練の芸人たちを前に彼はその能力を発揮できなかったようです。
私、テレビは嫌いですしバラエティ番組も嫌いですのであまり視ませんが、芸人さんたちの丁々発止のやり取りはまさにクリエイティブの真骨頂だと感じます。
そしてそこには、単なる言葉のコミュニケーションだけではなく、むしろそれはごく一部で、場の雰囲気、並び方、呼吸、表情、姿勢、タイミング、各人の疲労度、社会的地位や経歴、食前・食後など様々な要素が含まれており、単純な情報処理とは程遠い世界と感じます。
*
話は違うかもしれませんが、たとえば私も当直していて夜中に病棟から電話がかかってきます。簡単なことは電話対応だけですむこともあります。
でも、ちょっと考えるな―というときには、まずは眠い目をこすり病棟にフラフラ行ってみるのです。ナースステーションに入って座ってみると、雰囲気、モニター音などなどが身体の感覚を目覚めさせてくれます。
なんとなく、周囲がヒントを与えてくれている気がします。病棟に向かって歩くという運動も、脳をひっぱたいて動かしてくれるのかもしれません。
眠い所をうにゃうにゃ起きて歩く疲労感も、せっかく病棟まで来たんだからなんとかしなきゃと脳に覚悟を覚えさせるのかもしれません。
電話対応だけでは考えつかないような、クリエイティブな対応も出てくるかもしれません。そういった「場の力」は、重要だと思います。
結論から言うならば、世界に身体を没入させて世界に触れるという心的状態になることで、身体の発露で何らかの着眼点を見出し、発想の候補が少数だけ浮かび上がるということではないかと考えている。(P105)
世界に身体を没入し、そこで何を感じるかという考え方は大切だと思います。
自分の身体を世界に、さまざまな環境に、それは場所だけでなく深夜や早朝といった時間、あるいは忙しい作業や静かな休憩の中に投げ入れてみる。
身体は何を感じるか。疲れた、腰が痛い、腹へった、ねむい、帰りたい。最終的に感じているのは脳なんでしょうけど、これらは身体の訴えです。
身体の訴えはけっこう“ままならない”ことも多いものです。
それをどうするか、ということに気付くのもまた、身体かもしれません。こうすると疲労感が軽くなる、こうすると腰が痛くなく作業できる、こうすると空腹感が紛れる、仮眠をとろう、さっさと帰ろう。
世の中の多くの発明も、こういったところから出てきているものも少なくはないと思います。”天才とは1%のひらめきと99%の努力である”とエジソンは言いました。”1%のひらめき”はここから来るのです。
熱いものを触ったときに意識せずに手が引っ込む“反射”という機能がありますが、身体の感覚も反射的に身体が感じるものだと思います。
脳としては、その身体の訴えを退けないように、謙虚に感じ取る姿勢が大切ですね。身体の感覚を研ぎ澄まし、脳を謙虚にさせるという面では、瞑想やマインドフルネスも良いのかもしれません。
生活に即した用語で言えば、体験と経験を区別するということでもある。ニュアンスの微妙な差異であるが、体験という言葉は、実際に身体が直に接して影響を受けたことを指す場合が多い。一方、経験という言葉は、体験したことを基に、そこに本人なりの解釈や思考を交えて、昇華させたものごとを指す場合が多い。前者の方が、身体が直に接しているニュアンスが強く、より生々しい。(P122)
「経験」は、もしかしたら人がしているのをみて自分なりに解釈することでもできるのかもしれません。
ミラーニューロンというのが脳にあり、他人の動作をみていてもその神経細胞が活動して、自分でも同じ動作をしている気分?になるようです。見て学ぶことに関わっているのでしょう。
人から聞いた話でも経験することはできますし、あるいは小説を読んでも主人公の生き方、人生を経験することができます。そこから学んだこと、感じたことを次の現実の経験に活かすことはできるでしょう。
しかし、「体験」となると自分が身体を張って行動することが必要です。というか、そういうことを体験と呼ぶのでしょう。
そして、体験はまず現実と当って感じたこと、自分がどう動いたかということ。そして経験はその体験を思い返したり、これまでの知識や経験を踏まえて解釈したりすることによって形作られ、次に活かすことができる状態のもの、という感じでしょうか。
まず現実にぶつかるのが体験ですから、生身の身体がいろいろ“生々しい”感覚を受けとります。それに応じて感情も生まれます。
その“生々しさ”もその人の知識や経験によっても違うでしょう。初めての体験は新鮮ですが、慣れてくるとその”生々しさ“、新鮮さも薄れてきます。
体験で、得られる感覚が、つまり「体感」なのです。その「体感」や「感情」といかに向き合い、いかに解釈して「経験」とするか、が大事です。
では、体感に向き合うために、どうすればよいか? 私が提唱しているのは、ことばの力を借りて体感への留意を保つということだ。まずは、体感を言葉で表現してみることから始める。体感みたいな曖昧模糊としたものをことばで表現したって、正しくきちんと表しきれない! と多くの人が反論するだろう。その反論自体は正しい。しかし注目すべきなのは、「正しく、きちんと」表現することが必須なのではないということだ。(P132)
体感はすぐに流れ去るものなので、ことばで表現しないと如何にも刹那的になる。刹那的に感得することをただ繰り返す方が、ことばで表現しながら生きることよりも豊かなのか? 私にはそうは思えない。刹那的な各々の「今」の積み重ねから「学ぶ」からこそ、人は人として生きられるのだ、と思うのだ。(P134)
頭の中で考えたあるいは感じた思考や感情などは、すぐに流れ去るものですが、言葉にすると少しは定着します。とくに感情については、言葉にすることを強めることや、客観化ができるようです。
言葉にすることで、他の記憶や経験の同様の言葉で表すことができるものとつながります。「悲しい」という言葉を覚えると、悲しい状況に遭ったときに、同様に「悲しい」と感じた記憶をたぐりよせ、悲しみの感情が増幅されるのでしょう。
体感も同様で、言葉で表現することで定着し、記憶に残り、同様の記憶や経験と結びつきます。
「あせった」「飛び上がらんばかりだった」「はらわたが煮えくり返った」「ゾワッとした」でもなんでもいいですから。
すぐ流れさる刹那を繰り返し生きていくよりも、言葉として表現し、積み重ねて他の知識や経験と結びつける、つまり「学ぶ」から、より良い状態で生きていくことができるのです。
*
言葉では表せないこともあります。「暗黙知」というものもあります。そういった「知」を学ぶうえでも、たとえ、言葉にできない、といっても、ことばにするわけです。
ここでいう「ことば」は井筒俊彦氏や若松英輔氏がお使いになるように、いわゆる言語としての「言葉」よりも、より広く表現の方法をカバーした「ことば」なのだと思います。ジェスチャーや表情、身体動作や感覚などを含めて。
何を言っているんだか分からない説明になるかもしれませんが、どうにかこうにか言葉を出してみる。的確にその事象を表していなくてもよいのです。長嶋茂雄さんやイチローさんはそういう言葉の使い方をしていたのかもしれません。
「学ぶ」ことは、最初は「真似て」取り入れることですが、次は自分の「言葉にする」ことです。自分なりの言葉にしてみる。「自分の言葉にして理解する」とは「学ぶ」ということです。
そのためには、刹那刹那の体感を流れ去ってしまわないように言葉にして捕まえ、積み上げることが大切です。
我々の推論や意思決定を陰で支えているのは、実は感情や情動を司る中枢機構である。感情や情動を司る中枢機構は、間脳や大脳辺縁系といった、進化的に古い脳に存在する。その部位に損傷を負った患者は、論理的な推論機構により様々な場合分けを想起できたとしても、肝心要の意思決定ができない(つまり行動に移せない)という。(P172)
考え方の方向性を決めているは、感情や情動なのです。だから、同じ問題についても人によって考え方や結論が異なります。また、同じ人でもそのときの感情の状態によっても考え方が異なるでしょう。
そして、何かを決断するときも、この感情や情動が大切な役割を演じているということです。つまり、客観的な評価だけでは決断できない。
ある程度、「うーん」「いいね」「そうそう」「エモい」「ゲッ」「やな感じ」「キモい」「ちょっとねー」「(唾が出る)」「(腹が鳴る)」、などというのがないと、決められない。
善悪の判断が必ずしも客観的な評価にならないのも、このあたりが関係しているからかもしれません。
このような感情や情動機能を持たない、おそらく持つことができないAI殿はどのように物事を決めるのか、多数決か。
まあ、やはり客観的に多数決でもなんでもAIの意見を出してもらって、それを人間が決断の材料にする程度がいいのかもしれません。
そういえば、多数決というのは人間のAI化かもしれません。もちろん、全員が納得する結論を出すことは無理ですが、多数決というのはそういう方法で決まったらそれで決まりですよという約束のうえでの、一種の割り切りですね。
そういった中で、成田先生も提唱される「無意識民主主義」というのは、これはAIの本領を発揮して世の中のありとあらゆるSNSやメディアからの情報を集約し、意見を出すような仕組みですが、今の一部の人による投票制よりも、より多くの人々の意見を反映できるのかもしれません。
AIもそういった使われ方が幸せかもしれませんね。
*****
私はこの人間の身体の“生々しさ”、“ままならなさ”という舌を噛みそうな特徴が、人間らしさを造り、クリエイティブにつながる特徴だと確信しています。
人間の特産品である「脳」も、この“生々しさ”がその働きの重要な点を担っています。そのあたりは、『脳を司る「脳」』の紹介記事もご参照ください。
AIにこの“生々しさ”や“ままならなさ”ができるか。できないだろー。その辺りがAIの限界なのかなと思っています。