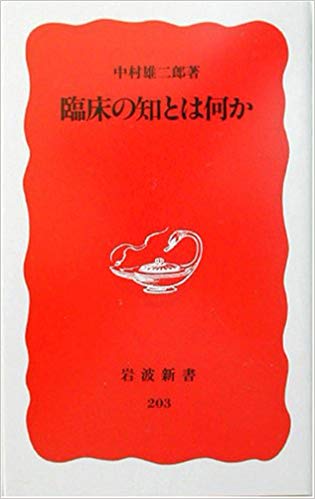
臨床の知とは何か 中村雄二郎 岩波新書
科学万能と考えられた時代は、最近すれ違ったかなと思っていたら、すでに遥か昔に過ぎ去りました。科学の発達による問題、あるいは科学では解決できないようなことが日常や仕事上の問題になることも多くなっています。
例えば公害やネット社会の諸問題は、科学技術の発達に伴い発生した問題です。さらに例えば親子や家族の関係や、仕事場での人間関係、あるいはお客さんや患者さんとの関係などは、社会科学や心理科学などある程度科学的に調査、介入できる余地はあるかもしれませんが、究極的には人間性の問題になるかと思います。
この本ではこれまで重用されてきて、技術文明を作り上げた「科学の知」から、実地での個人的経験や個人的解釈、あるいは行動してみての結果などをたよりに生み出す、いわばフィールドワークとしての知、すなわち「臨床の知」へと「知」の変換を提言していると思います。
「なんでも科学的に解決できるわけではないでしょー」「もっと人間性や物語性をもってお客さんや患者さんと付き合わないとだめでしょー」「世の中には暗黙知みたいなのがあって、よく分からないけど大事なものだと思う」「やっぱり患者さんと感情の触れ合いがあると、やりがいを感じるなあ」などといったことを一度でも感じたことのある方、必読です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フッサールは、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(1934-37)において、この問題を真っ向から扱った。すなわち、彼は述べている。学問の危機はなによりも、学問が<生>に対する意義を失ったことにあり、そのことはとりわけ、学問を単なる<事実についての学>に還元する実証主義的な傾向のうちにみられる。その動向は十九世紀の終わりごろから顕著に現われた。それに先立って、《十九世紀の後半には、近代人の全世界観は、もっぱら実証科学によって徹底的に規定され、また実証科学のもたらす<繁栄>によって徹底的に幻惑されたが、その徹底性とは、真の人間性にとって決定的な意味をもつ問題から無関心になり眼をそらす、ということを意味していた。》(P28)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事実として万人に認められることがらだけを取り上げ、普遍性のある情報を作り上げるのが「科学の知」であったと思います。
フッサールはこのように<事実についての学>一辺倒になり、学問が<生>に対する意義を失っていると述べています。
実証できないことは認められないという実証主義となり、実際に実証科学によって物質的な<繁栄>はもたらされているので、<人間性>に対しては無関心となるわけです。
その結果、<人間性>を無視した科学技術の繁栄により、公害などの問題が起こっているわけです。<人間性>を無視しなければ、こういった過度な問題は起きなかったのでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・・・彼のいう暗黙知とはなにかを示しておこう。そのことばでポランニーが言おうとしたことは、次の三点である。⑴われわれは、自分たちのはっきり言えることよりも多くのことを知りうるし、事実知っている。⑵このような知識は、われわれの個人的な裏付けをもっている。⑶われわれの認識の枠組みの実在性と性格は、焦点的にも捉えられず、われわれの行動のうちにただ副次的にあらわれるだけである。(P39)
このように、身体性をもち技能をそなえた個人の積極的関与やコミットが自然科学を含めた事物の認識、とくに生きているものの認識には不可欠なことが、M・ポランニーによって明らかにされたのである。(P43)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
実証できないもの、ゆえに科学的とはいえないもの・知識を、われわれは持っています。言ってみろ、つまり言葉にしてみろと言われても、なんとも言えない直感だとか、手加減、コツのようなものがあります。
身体が覚えているというものでしょうか。手取り足取り教えるというのは、こういった暗黙知を教える一つの方法なのかもしれません。
しかし、こういった微妙な知識が、自然科学とくに生きているものを相手にするには、不可欠であるということです。
相手が妻であったり、子どもであったり、お客さんであったり、あるいは患者さんであったり様々ですが、そういった生きもの相手には、科学的な判断だけでは、うまくいきません。
このあたり、どうやってもAIには分からないのではないかと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
さて<臨床の知>は、科学の知の三つの構成原理を先のように端的に、⑴普遍主義、⑵論理主義、⑶客観主義と呼ぶとき、そのそれぞれに対して、⑴コスモロジー、⑵シンボリズム、⑶パフォーマンスと私が呼ぶものを構成原理としている。(P133)
コスモロジーとシンボリズムとパフォーマンスの三つを特性あるいは構成原理とする<臨床の知>は、近代的な<科学の知>と対比して、次のようにまとめられることになる。すなわち、科学の知は、抽象的な普遍性によって、分析的に因果律に従う現実にかかわり、それを操作的に対象化するが、それに対して、臨床の知は、個々の場合や場所を重視して深層の現実にかかわり、世界や他者がわれわれに示す隠された意味を相互行為のうちに読み取り、捉える働きをする、と。(P135)
ことばを換えていえば、科学の知が冷ややかなまなざしの知、視覚独走の知であるのに対して、臨床の知は、諸感覚の協働にもとづく共通感覚的な知であることになる。
ところで、このような臨床の知は、科学の知が主として仮説と演繹的推理と実験の反復から成り立っているのに対して、直感と経験と類推の積み重ねから成り立っているので、そこにおいてはとくに、経験が大きな働きをし、また大きな意味をもっている。(P136)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そしてついに「臨床の知」です。“臨床の”といっても、これは医療における概念だけではなく、さまざまな場面で考えなければならないフィールドワークとしての知です。
「科学の知」の普遍主義、論理主義、および客観主義に対して、「臨床の知」はコスモロジー、シンボリズム、およびパフォーマンスを構成原理としています。
科学の知が普遍性を大事にし、分析的、客観的なものであるのに対して、臨床の知は個別性や場所柄もふまえて、隠された意味を相互行為のうちに読み取り、とらえるとのことです。
科学の知は、まさに数字や統計を使って事実を編み出そうすることでしょう。臨床の知はそれに対して、相手によってアプローチの仕方を変え、場面や場所の影響も考え、じっくり話し合って、なにが良いのか考えるといったところでしょうか。
例えば車屋さんが「科学の知」でお客さんを相手にすると、実情の売れ行きや人気、ネットでの評判、客の年齢、性別、家族構成、年収などからおすすめの車を考えるといったところでしょうか。
一方、車屋さんが「臨床の知」でお客さんを相手にすると、生い立ちだとか、人生観だとか、好きなものだとか、将来の夢や希望だとか、あるいは家族についてもどう思っているだとか、そういったことを話し込んで、こんな車はどうでしょうか、と提案する感じでしょうか。
また、ナラティブ・ベイスト・メディスンという考えがあります。これはまさに患者さんに対して、エビデンスがあるからこの治療!というのではなく、患者背景をていねいに聞き込んで、その患者さんに一番良いと思われることをするという考え方です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
いま、医療において患者は弱い立場にあると言ったが、それはとりもなおさず、患者が人間のパトス(受動、受苦、痛み、病い)という性質をもっともよく体現している、ということである。しかし、先に(第Ⅳ章第1節において)見たように、われわれ人間は身体をそなえている以上、精神=身体的存在である以上、どうしてもパトス性を帯びざるをえず、その点では医者にしても例外ではない。そしてむしろ、医者・患者関係も人間同士の関係であるかぎり、パトス性を帯びたもの同士の相互関係なのである。ところが、現代の医療では、そのような事実に目をつぶり、現実に背を向けるかのように、パトスを軽視し、とくに<痛み>の抹殺をおこなっている。これが今日の医療のもう一つの大きな落とし穴である。(P167)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
患者さんは病気により、痛みや苦しみといった人間のパトス(感情といってもいいでしょうか)を体現しています。患者さんを相手にする医師も人間です。ほんらい医師も人間である以上パトス性を帯びざるをえず、医師と患者さんの関係もパトス性を帯びたもの同士の相互関係のはずです。
しかし、「科学の知」を心棒にもつ現代の医療は、パトス性に目を向けようとせず、むしろ有害なものとして早く無くすことを考えます。痛みをスケールで数字化しようともします(ダメというわけではなく、評価には必要です)。
苦痛は無くなるのが患者さんにとってもいいことですが、その方法は鎮痛剤など、これまた副作用など気をつけなければならないものを使います。
表層では鎮痛剤などでとりあえずの苦痛消去も必要ですが、患者さんとのパトス(以下、感情に近い意味で使います)をもった付き合いも、深層では必要かと思います。
そういった付き合いのできる医療は、なかなか大病院の患者さんが多い状態では難しいかもしれませんから、日常的に患者さんを相手にするプライマリ・ケア医といった立場が重要なのかもしれません。
しかし、大病院で患者さんが多数でも、医師の考え方次第でパトスを持って患者さんを相手にすることは可能と考えます。ナラティブ・ベイスト・メディスンの考え方も徐々に広まってきていると思います。
単にエビデンスに基づいて医療を提供しているだけよりも、こちらもパトスで対応すれば、患者さんもパトスで答えてくれます。
患者さんが回復して血液データや画像所見が改善するのを見るのもうれしいですが、患者さんに笑顔がみられたり、お礼を言われたり、握手されたりするとうれしいものです。
その方が、いわゆる「やりがい」も感じられるのではないでしょうか。
******************
どんな仕事でもパトスをもって仕事をする、というのが、個別の経験を重ね相互関係からの知である「臨床の知」を生み出す、一つの要素かとも思います。
それはすなわち、パトス(pathos)を語源とするパッション(passion)をもって仕事をするということだと思います。